善本夏実さん(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)
地球惑星科学専攻での研究を通して
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 善本夏実
(2022年度地球惑星科学専攻修士課程修了)
地球惑星科学専攻に興味を持った理由ときっかけ
一つのきっかけは、中学校の理科の授業で"柱状図"を習ったことです。教科書やテスト問題に載っている柱状図を眺めるのが好きで、地面の下について考えることに興味を持ちました。高校時代は部活動と勉強に追われる日々でしたが、地学への漠然とした憧れは持ち続けていました。地学を学べる学部を探し、京大理学部への進学を決めました。
入学~系登録まで(1~2回生)
入学後2回生までは、理学科の学生としてどの専攻の講義も受けることができるため、様々な専攻志望の人と一緒に講義を受けました。そこでは何度も挫折感を味わいました。呪文のような数学の先生の話とそれに対して目を輝かせて質問する学生。休み時間に学生部屋でホワイトボードに数式を書き、いきいきと議論する学生。理学部に来る人ってこういう人たちなのか…と、驚きや不安を感じたのを覚えています。私は地学を勉強したかったため、地球物理と地質鉱物の授業を取りながら、自分のやりたいことを探しました。講義を受けていく中で、実際に目の前にあるものを観察することのできる地質をやりたいと感じるようになりました。課外では、アウトドアサークルに入り、パン屋でアルバイトをしていました。長期休みに2〜3週間の旅に出て、自転車を漕ぎキャンプをしました。サークルメンバーと過ごす時間や、見たことがない景色や食べたことのない食べ物、各土地の人たちとの出会いは何物にも変えがたく、大切な思い出です。

写真1:サークル活動(北海道での自転車ツーリング)
系登録から研究室配属まで(3回生)
地質学鉱物学教室は、少人数ですが、だからこそ手厚い指導を受けることができ、基礎から最先端の研究の話までを学ぶことのできる贅沢な環境でした。週末の巡検、同級生とのディスカッション、機器を用いた観察や実験は全てが新鮮でした。夏に実施された清澄巡検は、泊まり込み形式で、日中に沢を歩き、夜に製図を行い、地質図を完成させるという授業でした。地質図、断面図を完成させ、自分なりに地史を考え提出したときには達成感を感じました。足に入り込んだヒルとの戦いや、同級生との共同生活を含め、非常に充実した時間でした。講義を受けていくうちに、小さいスケールの岩石や鉱物から大きなスケールの地球の動きについて考えたいと思うようになりました。変成岩を構成する小さな鉱物の組織観察や化学組成の分析を行うことで、変成岩のたどった温度圧力履歴を明らかにし、そこから地球の造山運動について考えるという点は、まさに自分の勉強したいことだと感じ、岩石学講座を選択しました。
研究室配属(4回生)~修士課程
指導教員の河上先生に、フィールドと室内分析の両方に興味があることを伝え、研究が始まりました。研究生活は3年間丸々コロナ禍でした。人との交流が制限される中、1人暮らしの家と研究室との往復の生活が続き、精神的負担を感じる場面もありました。しかし、自分と向き合って考えることができ、自分の弱い部分を自覚できたことは非常に良かったと思います。そんな中、修士1年生の秋に、先生方や職員さんのご尽力により京大博物館で「大地は語る展」を開催することができました。「大地は語る展」は、一般の方向けに研究内容を伝えるアウトリーチイベントで、例年、地質学鉱物学教室の修士1年生が中心となって実施していました。コロナの感染状況を見つつ、博物館の職員さんや先生方と調整しながら準備を進めました。人数や展示方法などに制限はあったものの、無事開催することができ、来場者の方との交流を通じて専門分野の面白さを再認識し、研究のモチベーションにつなげることができました。そして何より、院生同士の仲が深まったことが非常に嬉しく、良い思い出になっております。私は岩石が変成作用を受けて部分的に融解するような条件下で、岩石と共存する流体相について調べていました。これらは実験ではなく、過去にそのような条件にあった岩石から証拠を見つけ出す手法を取ります。微小な鉱物や流体包有物の分析は根気のいるものでした。目標を見失ってしまうときもありましたが、研究が停滞しても毎日大学に通うことを意識し取り組みました。岩石組織を観察し、文献調査とディスカッションを通じて過去の地下の現象について考察する過程はとてもわくわくし、これこそ自分がやりたかったことだと思いました。このことは本当に幸せなことだと思っています。研究室の先生方の熱心な指導や、周囲のメンバーからの刺激に感謝しています。

写真2:「大地は語る展」当日の様子
現在の仕事
現在は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の職員として働いています。入構時から約1年間、資源探査部という部署に所属しています。資源の乏しい日本に安定的に金属資源を供給することを目指し、海外の企業や政府機関との共同調査や、日本企業への探鉱支援を行っている部署です。1年目から海外での現地調査の機会もあり、やりがいを感じています。学生時代は鉱床地質にあまり触れる機会が無かったため、初めてのことが多い一年でしたが、研修制度も充実しており、環境に恵まれていると感じます。まだまだ学ぶことが多いですが、地質のみならず世界情勢や資源の需要動向を把握し、視野を広く持って深く物事を考えることができるようになりたいです。

写真3:オーストラリアでの現地調査の様子
地球惑星科学専攻の経験で現在生かされていること
私は地質の分野を活かせる仕事を選んだため、文献調査や地質調査、岩石鉱物の観察や分析等の経験は、もちろん役立っており、嬉しく思っています。ただ、どの分野に就職しても相手の考えを理解し自分の考えを伝える能力や、資料作成、文章作成能力は同様に求められると思います。学生時代のゼミや学会発表、卒論、修論等の作成の経験が生きてくるのではないでしょうか。大学で出会う人はとても自由でした。他者の目に振り回されず、自由な思考を持って行動する人たちと接する時間は刺激的でした。学生のうちに、先生や学生はもちろん、色々な背景を持った人たちとコミュニケーションを取っておくことも後々に生かされるのではないかと思います。
(執筆日:2024年5月27日)
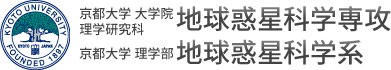
 MENU
MENU