伊丹柚さん(大阪市立科学館)
地球惑星科学専攻での研究を通して
大阪市立科学館 伊丹柚
(2021年度地球惑星科学専攻修士課程修了)

写真1:仕事の様子
地球惑星科学に興味を持った理由
初めのきっかけは、幼少期に祖父に鉱物が付録の雑誌を買ってもらったことでした。幼いながらにも一つ一つ違う鉱物の色や形が不思議で、ずっと石を眺めていました。高校時代には、修学旅行でアメリカのカルフォルニア科学アカデミーの自然史博物館へ行きました。初めての海外の大きな博物館に感動し、博物館の仕事に興味を持ちました。その際に図鑑や鉱物標本を買って帰り、受験勉強の傍ら眺めるうちに、幼少期から好きな鉱物のことを結晶学的に研究したいと思い、進路を決めました。
大学での学生生活
学部時代は信州大学で2年半、京都大学で科目等履修生として半年、岡山大学で2年過ごしました。5年かけて3か所の大学で単位を取得し、学位を取りました。信大では、野外巡検とサークル活動の交響楽団が生活の中心でした。3年生の時、鉱物や岩石の成因についてより専門的に学ぶため、3年次編入を決意しました。編入学までは、京大で科目等履修生となり、鉱物学や岩石学の授業を履修しました。京大の授業はとても刺激的で、専門的な知識が増えていくのが楽しくて、一生懸命勉強しました。岡大に編入後は、変成岩岩石学の研究室に所属し、卒業研究では、地球内部で超高圧の変成を受けた中国蘇魯地域のザクロ石カンラン岩の具体的な温度圧力履歴について研究しました。電子プローブマイクロアナライザーで岩石を構成する鉱物の微小領域から化学組成分析を行い、地質温度圧力計を用いて過去にその岩石が経験した温度圧力履歴を推定しました。研究試料が地下でどのような温度圧力履歴をたどり、地上に現れたのかを検討することに興味深さとロマンを感じました。
大学での研究生活
修士課程は、再び京大で過ごしました。修士論文では奈良県天川村産レインボーガーネットの結晶構造モデルについて検討しました。レインボーガーネットは表面が虹色に輝く鉱物で、結晶内部でアルミニウム量が数百nmでの周期的変化を示すために可視光の干渉を引き起こすことが知られていますが、結晶構造レベルでどのような変化が生じているのかは明らかになっていません。そこで新たに高分解能電子顕微鏡での研究に挑戦し、様々な結晶構造を仮定した電子顕微鏡像計算シミュレーション結果と比較する方法で、レインボーガーネットの虹色の要因であるアルミニウムに富む領域と乏しい領域それぞれの結晶構造を検討しました。様々な条件を検討し、色々なパターンで何度も試しましたが、結果が出ない日々が続きました。加えて、修士1年の終盤からはコロナ禍に突入し、研究が進まない時期もありました。研究には、誰も知らないことを発見する面白さや楽しさがある一方、想定以上の苦労がありました。しかし、指導教官をはじめとする鉱物学教室の皆様の知見をいただきながら、諦めずに実験を重ね、最終的には1つの結論を出し、修士論文として結果をまとめることができ、大きな自信になりました。また、修士課程では、研究以外でも鉱物と関わる機会が多くありました。京都大学総合博物館では、子ども博物館というイベントで、自身考案のオリジナルワークショップ「鉱物ぬり絵でオリジナル図鑑を作ろう!」を定期的に開催し、活動を通じて、子どもたちに鉱物の魅力や面白さ、自身の研究について伝えました。「地の宝II比企鉱物標本展」開催の際には、博物館の収蔵庫で数々の貴重な鉱物の標本整理や展示作業などをお手伝いしました。先生方や研究室の仲間と毎日のように博物館で作業し、展覧会成功に貢献できました。このように鉱物学教室ならではの経験が多くでき、大変有意義な時間でした。

写真2:地の宝Ⅱ比企鉱物標本展
現在の職務
修士課程修了後、会社員を経て、現在は大阪市立科学館で働いています。学生時代から博物館で働くことへの憧れがあり、ご縁があり転職しました。 「博物館で働いている」と言うと「学芸員ですか?」と度々聞かれますが、私は学芸員ではなく、事務職員です。私自身も「博物館で働く」=「学芸員」というイメージでしたが、実際に働き、博物館には限られた人員で幅広い業務を行う職員の存在があることを知りました。私の主な仕事は、広報です。仕事内容は科学館のホームページ作成や出版社・新聞社から届く記事校正、ポスターチラシ等の広報物作成、マスコミ取材の対応、SNSでの発信などです。加えて、問い合わせやトラブル対応などもあり、多岐にわたる上、細かなルールの理解が求められます。いつか、学芸員になりたいという思いもありますが、現状は広報担当として科学館の運営に携わることができ、大変誇りに思います。
地球惑星科学専攻の経験で現在生かされていること
研究生活の中で、粘り強く努力することの大切さを学びました。京大での研究生活は、入学当初は周囲との知識の差を感じましたし、途中でコロナ禍に突入するなど異例な事態もあり、想定していた研究生活が送れない時期もありました。しかし、そのような状況でも指導教官をはじめとする鉱物学教室の皆様に支えられながら、粘り強く努力を重ね、自分の興味を追究できたことは人生の中で大きな財産です。そしてその経験もあり、今では自分の夢に一歩近づくことができました。また、京大総合博物館での様々な活動も、大いに今の仕事に生きています。活動を通じ、相手に興味を持ってもらうには、まずは相手の目線になることが大切だと学びました。その経験から仕事で人々に科学館の魅力を広報する時にも、PR対象の目線になり、内容や手段を考えています。科学館は一般に子どものための場所と思われがちですが、大阪市立科学館は大人目線で作られている展示も多く、大人だからこそ興味が湧くポイントもあります。子どもにも大人にも、1人でも多くの人に「科学って面白い!」と思ってもらえるよう、多くの魅力を伝えていきたいです。

写真3:子供博物館での活動
(執筆日:2025年4月18日)
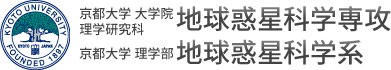
 MENU
MENU